▶思えば遠くへ 「2024年初夏の旅①」(高22期 加藤 麻貴子)

久しぶりに長めの旅行をすることにしました。子どもたちも独立し、同居の両親も見送った2003年頃から時々旅行を楽しむようになっていましたがここ3年はコロナ蔓延のために断念しておりました。遠くにいくこと、横須賀発着の九州東京湾フェリーを使うこと、それから瀬戸内海を昼間クルーズすること、この3点をコンセプトに年明けから連れ合いが計画を立て、乗り物やホテルの予約を入れてくれました。実は詳細はあまり知らずに私は出発したのでした。
・5月10日(金)晴 05:30横須賀発―09:00名古屋―16:00大阪着 三井ガーデンホテル泊
自宅を車で出発、名古屋辺りまでは順調に来たものの道路整備などで車線が減り渋滞が続き、四日市からはパーキングエリアもなく思いのほか時間がかかったけれど大阪に無事に到着しました。私が運転するわけではありませんが、今回の旅の中でこのドライブが一番の難関でした。ホテルは土佐堀川と堂島川に挟まれた中州にありました。
おなかも減りホテル近くの停車中のタクシーに「ぼてじゅう」を問うと「わかりまへんがな」とのこと、それは諦めて周辺をウロウロしていると先ほどの運転手が「まだ決まらんのかい?スマホで検索して見せてくれたらいけるかもしれへん」と声をかけてきました。関東ではけしてない光景で大阪らしいと思いました。
近くの中華のお店に入りましたが、QRコードを読み取り注文をするということです。この方式の注文にもこれからは慣れねばと、不安ながらトライし無事に注文できました。私は胃腸が疲れていたのでお粥を注文、とてもコスパの良いお店で若い男性会社員がわいわいがやがや賑やかな大阪らしい雰囲気での夕食でした。
土佐堀川沿いに石造りのオブジェや花壇のある平成元年に造られた公園通りがあり、色とりどりのバラが美しく散歩を楽しみました。
・5月11日(土)晴→曇り Asia Trading Center in 大阪ー12:15三井サンフラワー”くれない”出航―13:45左舷に淡路島ー14:50播磨灘通過ー15:50右舷に豊島(てじま)ー16:00左舷に四国丸亀ー19:00来島海峡大橋通過ー24:00別府着ー船中泊ー12日08:00下船
フェリーに乗船すると京都利休の松花堂弁当のサービスがあり、久しぶりの和食は美味しく全部食べることができました。安心のために酔い止めの薬を服用し、少し荒い波の大阪湾を抜けると明石海峡大橋をくぐり瀬戸内海を進み始めました。次々に現れる淡路島、小豆島、倉橋島の島々と瀬戸大橋、しまなみ海道の来島海峡大橋などを眺めながら日は暮れていきました。
こんな巨大なものを造った人間の凄さにわくわくしながら橋梁の下を通りました。船は大浴場や音楽の演奏もあり快適でした。
夕食はビュッフェで少し食べ過ぎたようで胃腸を重く感じました。
・5月12日(日)曇り→雨 08:00別府下船ー09:00国東半島杵築(創業1900年の綾部味噌店ー武家屋敷)ー11:10宇佐神宮ードーミーイン大分泊
真夜中に別府に到着して船中泊、下船は朝の8時、案内放送を待って車両階に行くと殆どの車はすでに下船しておりました。曇り空のなか、とりあえず国東半島の杵築に行くことにしました。Naviの言うままに進むと閑静な住宅街に導かれ、まず目についた創業1900年の綾部味噌店、店主にこの辺りの様子を伺うと、綾部味噌屋は元は豪商志保屋の屋敷で味噌屋になる以前はお酢を造っていたそうです。
18世紀末の町家建築でどっしりとした店構えに昔の縁を感じました。ご店主の好意で店の駐車場に車を置かせてもらい周辺を散策、店のすぐ隣の「酢坂」という急な坂道を登ると武家屋敷群、うっそうとした木立に囲まれた屋敷が続きます。実際に住人がいるにも関わらず庭を解放したり、トイレも整備されていて感心いたしました。
杵築城も尋ねたかったのですが、雲行きが怪しくぽつぽつと天から落ちてきましたので諦めて次の目的地の宇佐神宮に向かうことにしました。途中、高地を走る高速道路は濃霧に包まれ先行車のテールランプを追いかけるように進みました。
宇佐神宮は創建725年、全国四万社の八幡神社の総本宮で日本一大きい石の水盤にきれいに並べられた柄杓で手を清めて境内に入り国宝の本殿に向かいました。千古斧入らぬ杜は深く広大で植生豊かな木々が雨の雫と共に醸し出す深淵な空気に包まれ本殿に向かいました。
残念ながら上宮は修復中でその威容に拝することはできず幕越しの参拝でしたが、美しく優しいたたずまいの下宮を参拝し満足いたしました。作法は一般と異なり二拝四拍手一拝でした。しかもその四拍手は大振りに勢いよく叩きます。
8世紀ごろ律令国家の建設に反対する隼人の反乱を治めるために八幡神を神輿に乗せ制圧に向かったとされ、神輿の発生の由来となったそうです。また隼人との戦いで殺生の罪を悔いた八幡神が仏教に救いを求め、宇佐で神と仏が習合したと言われています。神仏習合とはこのことかと古希を超えて初めて知りました。修復工事の終了とともに来年は開山1300年祭が盛大に行われるようです。








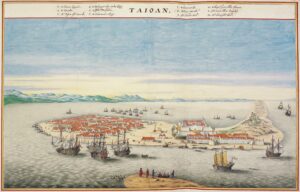

写真を拝見する限りでは外国人観光客の姿がないようですが、その辺りはどうでしたか。彼らはSNSの情報に偏るから、それを逆手にとって空いている観光地をゆったり旅するのが良さそうですね。
堂島・中之島や北新地界隈は、30代前半まで8年間の大阪支店勤務時代に徘徊したので良く知っています。昼食は隣の関電の食堂に毎日通ったこのでした。年子の幼子2人を連れて家内が始終実家に帰っていたので、梅田から中之島までの地下街の食事処にもすべて入ったことがありました。
「ぼてじゅう」はお好み焼きでしたかね。当時は「千鳥」が人気店でした。が、40年も経った今ではずいぶん変わっているでしょうね。
大分には中村道也君(高22期4組)が住みついていますよ。連絡して穴場を聞く手がありましたね。
仕事で大分空港(確かホバークラフトを使った)から北九州市まで高速バスに乗った時のこと、しばらく走ったら前を行くバスから乗客一人が道路に降り、当方のバスに乗り移ったことがありました。さすが田舎は融通無碍でイイなあ、と思ったものでした。
続きを楽しみにしています。
大阪と阿蘇のホテルは外国人が多かったようです。阿蘇では西洋の人も多分台湾の人と思しき人たちが多くいました。「千鳥」は以前に行ったことがあります。連絡先を知っていれば中村道也君に聞く手もありましたね。九州に行ってみて彼が住み着いた気持ちが分かるような気がしました。とても良いところでした。
高橋君は大阪にも住んでいらしたのですね。幼子ふたりの子育てを慣れない土地でするのは奥様は大変でした。ご実家に時々帰してあげるのは息抜きになってよかったと思います。その頃は私は子育て、介護に家業と毎日雑事に追われ同じ市内に住みながら実家にあまり顔を出すこともしなかったので、今思うと両親には不義理をしたと後悔することもあります。外食三昧も舌が肥えて良かったとおもいます。