▶400年前に日本が台湾を領有したかも知れない話 そのⅠ(高22期 高橋克己)
5月の拙稿「駆け足で振り返る『台湾400年史』」の冒頭で次のように書いた。本稿はその『浜田弥兵衛事件』の顛末である。
「台湾の英語名『Formosa』は、大航海時代にこの島を見つけたポルトガル船員が『Ila Formosa(美麗島)』と叫んだことに由来する。台湾が西洋の歴史に登場するのは1624年にオランダ東インド会社が台湾を統治してからのことで、この頃『浜田弥兵衛事件』(タイオワン事件)と呼ばれる日蘭対立事件があった。この時に幕府がもう少し強硬に出ていたら、日本が台湾を統治していた可能性もあった。」
参考文献として、『十七世紀日蘭交渉史』(天理大学出版部1956年刊)、『バタヴィア城日誌1』(東洋文庫1970年刊)、『東インド会社とアジアの海』(講談社学術文庫2017年刊)、『倭寇―海の歴史』(講談社学術文庫2012年刊)などを用いた。
■大航海時代と東インド会社
本格的な大航海時代は、ポルトガルのヴァスコ・ダ・ガマ(1469年?~1524年)が、1498年にアフリカ南端の喜望峰を回ってインドのカリカットに到着したこと、そして20年余り後に同じポルトガルのマゼラン(1480年~1521年)が、南米大陸南端の海峡を抜けてフィリピンに到達したことをもって嚆矢とする。それらはまた、従前のインド⇒ヴェネチアという複雑な貿易ルートを、単純なインド⇒リスボンの海路ルートに変更させ、百年経たぬうちに北西欧州各国が「東インド会社」を設立する契機となった。
ガマの帆船二隻がインドから持ち帰った宝石や香辛料などの収益は、2年間の航海費用を賄ってなお大きな収益をもたらした。リスボンにいたフィレンツェ商人は「これでヴェネチア人は、東方貿易を辞めて漁師をやらなければならなくなるだろう」と故郷への手紙に記した。大量の物産を直接インドから欧州に輸送することによる様々なメリットを予見していたのである。
実際、ガマ以前の東インドの香辛料は、一旦インドのカリカットに集められた後、ペルシャ湾・紅海(船)⇒シリア・エジプト(陸路)⇒地中海(船)⇒ヴェネチア(陸路)⇒欧州各地という迂遠な交易ルートを辿っていたために、幾多の業者の介在、荷の積み替えや関税などに加えて、これらをヴェネチア商人が独占していたことで当然高価になった。
アフォンソ・デ・アルブケルケ麾下のポルトガル艦隊(事実上は海賊)は、1503年から1515年までにインド洋海域のソファラとモザンビーク(東アフリカ)、ホルムズ(ペルシャ湾)、ゴア(インド)、マラッカ(マレー半島)などを次々と襲撃し、アデン(紅海)とディウ(北西インド)を除く主要な港町を軒並みポルトガルの支配下に組み入れた。が、彼らが独占したのは香辛料貿易だけで、多様な敵を相手にした種々雑多な商品全ての独占まではできなかった。
この時代に「海」を介して取引された物産には、東インドの香辛料(⇒中国・西アジア・欧州)の他にも、南北アメリカ大陸の銀(⇒中国・インド・欧州)、中国の茶や絹や陶器(⇒東南アジア・西アジア・欧州)、インドの綿織物(⇒アジア・アフリカ)、アフリカの奴隷(⇒新大陸)、日本の銀(⇒中国)などがあり、日本は銀と引き換えに中国の生糸や東南アジアの染料・香木、台湾の鹿皮などを輸入した。
これらの交易に関わった「東インド会社」は、1601年(以下、断りない限り1600年代)の英国と翌年のオランダを皮切りに、フランス、デンマーク、スウェーデン、オーストリアが17世紀半ば以降に設立した。ポルトガルも28-32年の短期これを置いたが、1581年にスペイン王フェリペ2世が断絶したポルトガル王を兼ねて事実上スペインに併合されたため、徐々に勢いを失った。
そのスペイン・ハプスブルグ家の支配下にあったオランダは、16世紀前半の宗教改革の影響を受けた新教徒だったことから、カトリックを強要するスペインに反発し、48年に独立が認められるまで戦争を続けた。アムステルダムやロッテルダムなどの港町には、この戦争によってイベリア半島の港への出入りを禁じられた大勢の船乗りや漁業者、海運業者らがいた。
その頃、ポルトガル船に乗り込んでアジアを見聞してきたリンスホーヘンの『葡萄牙人の東洋航海記』がアムステルダムで出版された(1595年)ことも、ポルトガル船に乗っていたオランダ人たちの東洋熱を刺激した。そこへ、オランダに流入したベルギー・アントワープの新教徒(裕福な商人、金融業者、手工業者ら)が加わり、独自に大型船を建造・艤装して東インドを目指すこととなった。
02年に誕生したオランダ東インド会社(以下、VOC)はアムステルダム、ロッテルダム、ミッデルブルグなどに拠点を置き、従前から東方貿易を行っていた6つの会社の合併会社である。オランダ政府から喜望峰周りの貿易を独占する特許状が与えられ、議会から東インドで要塞を建設する権利、総督を任命する権利、兵士を雇用する権利、現地の支配者と条約を結ぶ権利が与えられた。つまり、ミニ・オランダが東インド各地に置かれたのである。
VOCは09年に平戸オランダ商館を開設、10年後に第4代VOCバタビア総督クーン(在任19-23年、27-29年)がジャワ島西部のジャカルタにバタビア要塞を築き(21年完成)、多くの吏員や軍隊を配してアジアの本拠地とした。以降VOCは、台湾、ベトナム、タイ、カンボジア、バタニ、マラッカ、ビルマ、インド、ペルシャ、アラビアなどの各地に商館を設け、商船を派遣して貿易を拡大させた。
■平戸オランダ商館
徳川幕府以前の日本の交易に目を転じれば、一つは16世紀前半から日本の銀と明の絹を交換した勘合貿易であり、他は倭寇だった。倭寇は13世紀から16世紀にかけて東シナ海から南シナ海の朝鮮と中国沿岸で略奪を行った海賊で、15世紀初めまでの前期倭寇とそれ以降の後期倭寇がある。前者が日本人中心だったのに対し、後者には東シナ海沿岸の人々に日本人、そしてインド洋海域でもまさに海賊だったポルトガル人が混じり、台湾西海岸一帯も倭寇の根城だった。
徳川幕府は、明の「海禁策」(倭寇対策)などのために16世紀半ばから途絶えた勘合貿易やその後のポルトガル・スペイン相手の南蛮貿易に代えて、04年から東南アジアを相手とする朱印船貿易を行った。35年の「第3次鎖国令」(外国船の入港を長崎のみに限定し、日本人の渡航や帰国を禁じた)までの30余年間に、交趾・安南、暹羅(タイ)、呂宋・高砂などに350隻余りの朱印船を送り出した。
39年の「第5次鎖国令」で、かつて種子島に鉄砲を伝えたポルトガル船の入港を禁止し(スペインとは24年に断絶)、オランダにのみ出島での商館運営(41年に平戸から移転)を許した背景には、カトリックの男子修道会「イエズス会」の布教姿勢への強い警戒があった。英蘭両国が、マカオを拠点とするポルトガルの暴挙を幕府に流した背景もある。
「400年前に日本が台湾を領有したかも知れない話」には、平戸のオランダ商館とバタビアのVOCが大いに関係している。幕府は09年にVOCと平戸に朱印状を与えた。これを受けて平戸城主松浦隆信はオランダ商館を開設し、41年に出島に移転するまでの30余年間、平戸はVOCの貿易拠点となった。
背景はこうだ。スペインは08年、現状維持を条件とした12年間の休戦条約案をハーグのVOCに届けた。VOC重役会(17人会)は南洋にいた艦隊司令官フェルフーフェンに各地との交易開始を命じた。その一隻が翌年平戸に着き、家康から朱印状を受けてスペックス(29-32年バタビア総督)を初代館長とするオランダ商館が開設された。当時の日本では、1570年からポルトガルが長崎で、スペインは家康の命により薩摩諸港から浦賀に移って、それぞれ貿易を行っていた。
13年6月に平戸に入港した英国東インド会社の船に幕府が朱印状を与え、8月にコックスが平戸に英国商館を設けたことはVOCの脅威となり、16年に幕府が交易を長崎と平戸に限るに及んで、日本を舞台にした英蘭西葡の競争は一層激化した。19年7月に至り、英国王の提案で英蘭は防守同盟を結び、20隻の艦隊を編成して西葡の植民地を襲い、海上でもマカオ(葡)・マニラ(西)の敵艦船を襲撃した。が、英国は24年1月、貿易の不振を理由に平戸から引き上げた。(続く)


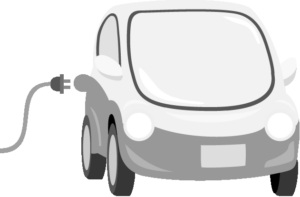

平戸はとても遠い。2019年に長崎に行きました。長崎から電車で1時間30分で佐世保に、さらに2時間バスに揺られて平戸に着きました。復元された平戸オランダ商館も見学しました。立派な建物で当時の貿易が盛んだったことが偲ばれました。日本に南から来る船舶には便利なところですが、幕府にとってはとても遠い。それは安全にも繋がったのかと思いました。
最近友人がマカオ、香港を経由して深圳に行きました。マカオではポルトガル語、香港では英語はあまり聞こえず広東語、深圳では中国語の普通話が聞こえたそうです。そして香港から深圳に入るときにはとても緊張したそうです。
400年前のアジアの事情がその片鱗を言葉に残していると思いました。
平戸商館が置かれたのは1609年-1641年の32年間、オランダの台湾統治は1624年-1662年の38年間で、どちらも400百年のほんの一瞬なのだなあ、と改めて実感しました。ですが、平戸商館も台南のゼーランジャ城も、今も残されています。
加藤さんがお住まいの浦賀の歴史も大したものです。ブログには書きませんでしたが、家康は、それまで薩摩諸港に出入りしていたポルトガル船の寄港地を浦賀に移した。と参考文献に書いてありました。私は全く知りませんでした。