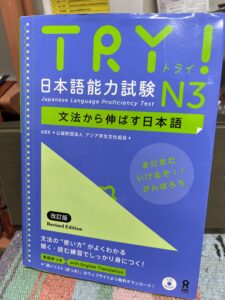▶[小説]床屋の事件簿9(高22期 伴野明)

剛田さんと目があった。剛田さんはソファから身を起こして言った。「そこんとこですよ蓮池会長が私に何度も話してくれたのは」
「そ、それでどうしたのよ武さん、聞かせてよ」と、松井さんが急かした。
「オレ一人で行くことにした」武はきっぱりと言った。
「一人でって、そのころの横須賀って、とんでもなく不気味なとこだぜ、私、一度行ったことあるけど、あのドブ板通りって、変な店とベロベロに酔っぱらった米兵だらけで、怖くて入り口から中に入れなかった……えぇ、ほんとにあそこに一人で行ったのぉ?」松井さんはたまげて目をむいた。
「そう、……一人で行った。オレ、よーく考えた。一人の方がむしろケンカになる可能性が低いって。もしオレ一人を横須賀が袋叩きにしたら、それはオレの勝ちだって思ったんだ。怪我はしても死ぬことはねえだろうとも考えた。オレが勝つ可能性はそれしかないって結論さ」
「すげえ度胸だ」野中さんは驚いた。
「ここからが佳境だな」松井さんをはじめ、みんながソファから起き上がった。
「ふふっ、あれは土曜日の昼だった。オレはいつものメットをかぶってドブ板通りの入り口にいた。過去ドブ板には一度だけ行ったことがあった。その時は夜だった。米兵がうごめく通りを見て、足が止まった。なんだろう、なんて不気味な、アメリカが吐き出すヘドみたいなものがそこらじゅうにベタベタくっついているような、いちど入ったらそれが体中にくっついてしまうような、怖いというより、とにかくいやな町だ。こんなとこにまともな人間がいるなんて思えねえ。でももうここまで来ちゃった。入るしかねえんだ。
横須賀連合のたまり場はドブ板通りのド真ん中、竹林っていうスナックと聞いてた。オレは怖さを吹き飛ばすために、思いっきりエンジンを空ぶかしした。近くにいた横須賀のヤツらが気付いて、止まってたバイクに飛び乗ってワサワサ奥へ入っていくんだ。竹林にいるヘッド(マイケル)に知らせに。――オレのメットは集会で目立ってたんで、連中もすぐわかったらしい。赤と紺の、そのころはめずらしいフルフェイスだったからな。オレはちょっと間をおいてからゆっくりとドブ板に入っていった。
しばらく行くと暴走バイクがビッシリ集まってる店が見えた。あれが竹林だろう。オレは一回バイクを大きく空ぶかしして竹林の前に止まった。例のプロレスラーみたいな連中が三人立ってた。真ん中のヤツは見覚えがある、黒人で顔に鳥の翼みたいなタトゥーがあった、こいつは副ヘッドだ。
オレはゆっくりメットを脱いだ。不思議だった。怖さってものはドブ板に入った瞬間から完全に消えてた。体から心が離れて浮いているような感じだ。体の少し上に心があってすごく冷静に自分を見つめてる。――『マイケルさん居るか?』と、オレはひとことだけ言った。自分ながら、これ、オレがしゃべってる言葉じゃないなと感じながら。
副ヘッドは黙ったまま『マイケルは奥だ』と親指で示した。オレは真っすぐ入り口に向かって歩き出した。すると連中がサーッと開いて道ができた。その瞬間、オレ、コイツら全員に勝ったと思えたんだ、あとはマイケルがどれだけの人物か、それが見たい。
店の奥にマイケルが座ってた。きょうはサングラスをしてねえ。オレとマイケルの目が合った。オレは一直線の視線に新たな不思議な感覚を覚えた。言葉を発しないのにマイケルと話し合ってるような。――そのまま数分たった時、マイケルが目をそらした。そして『分かったよ東条さん、ケンカはしねえ』と、マイケルが言った。オレはその言葉にすぐ反応した『ありがとう、そう言うと思った』と言って(やっぱりこれ、自分が話してるんじゃない)と感じた。マイケルとオレの心の会話だったんだ。そう思った瞬間、笑顔が出た。マイケルもやっぱり笑顔を返した。そしてオレは我に返った。マイケルと握手して、お互いバンバン肩をたたいた。完全な和解だ」と武は当時を思い出して感慨にふけっている。
「フーッ、どうなるんだと思って聞いてた、暴力はないけど究極の対決だったんだね」と、野中さんがため息をついた。
「マイケルとはそれ以来、すごく仲良くなった。ヤツも横浜との抗争をなんとか避けようと悩んでたと言ってた。残念ながら、ヤツはアメリカに帰っちゃったけどね」と武は残念がった。
「あの横須賀に一人で行って話をつけてくるなんざ、映画の世界だよ。ヤクザの世界だって現実にはありえねえ」と剛田さんは、武本人の話に改めて感動したようだ。
「その後の横浜連合はどうなったの? 当然、武さんが全体のヘッドでしょう」と松井さんが尋ねる。
「いや、ツーヘッドは変わらなかった。というより、そのころオレは暴走族引退を考えてたんだ。あと半年で二十歳になる。そこが区切りだとね。もう一つ、その時勤めてる会社がオレに転勤するようにと言い出した。名古屋の事業所を拡張するんで、そこで係長をやれってんだ。会社的には昇進で給料も大卒並みにかなりアップする。その部署の人員から考えたら数年で課長になるのは間違いない。悪い話じゃないだろうって。ところがな、オレ、そのころ独立することを考えてたんだ。それが『床屋』ってわけだ。純粋に自分の腕だけでできる仕事がしたかったのよ。すでに理容師専門学校に入ることを決めてたし」と武は言う。
「へぇー、それもすごいな、オレだったら絶対出世コースを取るな」野中さんがまた驚いた。
「驚きついでにさ、武さん、奥さんをいつごろどうやってゲットしたのよ?」と聞く野中さんに続いて松井さんもニヤけて聞いた「オレも聞きたかったのよ、奥さん美人じゃん……」
「ちょっと、今日はその話は『無し!』――暴走族まででいいじゃん」武はテレまくって逃げ始めた。ところが剛田さんが逃がさない。
「そこ、深いでしょう、蓮池会長からちょっと聞きました。まだ時間あるじゃないですか、話してくださいよ」という。
「まいったなー、話さないと帰してくれない雰囲気じゃん」武はしかたなく話始めた。
「尚子は会社の近くの百貨店の化粧品売り場でアルバイトをやってた。オレ、たまたまそこに行ってビックリしたよ。すごい美人に見えたからね」武はテレながら話す。
「いやぁ、尚子さんって、若い時だったら絶対女優クラスの美人だぜ」と松井さんが真顔で話す。
「とにかく、一応キレイだったよ。そのうえ話してみると感じいいんだよ。それからっていうと、もう、なんか理由つけて何度も何度も会いに行くのよ。わかるだろ……さすがに尚子も意識し始めてさ、ちょっと態度が変わってきたのよ。あいつ、急によそよそしくなったり、親しそうになったり――試してたんだよな。それでオレもそろそろ頃合いだなと思って、食事に誘ったんだ。そしたら一発オッケー、そのままホテルよ。実はオレ美里っていう娘と付き合ってたんだけど、尚子一筋になっちゃった。結婚したいよなって思ったんだが、最大の問題は仕事。――オレ、床屋になるって決めてたから、会社を出たら、専門学校を卒業しても新米の理容師でしかない。経済力、全然ないじゃん。尚子と付き合いだして彼女も本当の事を話してくれた。オレの前にある人と付き合ってて、結婚を迫られてるっていうのよ。そいつを好きなのかって聞くと『きらいじゃない』って。どんな男かって聞くと、特に美男子じゃないけど、ガッツありそうで男気があって、家は金持ちっていう。オレ、まいった、状況最悪じゃん。これって勝負にならねえ。どうやったら尚子を取れるか悩んだ、悩んだ。悩んだ末、オレは尚子に提案した。『たのむ、一年だけ待ってくれ。一年後に理容学校を卒業して、全国新人理容コンテストでオレは必ず一等を取る、そうなったら結婚してほしい』ってな、それに尚子は『ウン』といってくれた」と、武は思い出して少し目が潤んでいる。
「武さん、結果は?」松井さんが遠慮がちに聞いた。
武は少し間をおいて答えた。「うん、一等賞、取ったよ……人生で一番本気だった一年だった。大手の理容店五店から声がかかったよ、すぐ採用したいってね、給料も新米理容師としては破格だった」ぽつりぽつりと、武の話しかたが変わった。ちょっと違和感を感じた野中さんが尋ねた。「武さん、なんか嬉しくないみたいだけど……?」
「そぉ、……そのあと思いがけないことが分かったのよ」武はずっと下を向いて話している。
「何ですか?」野中さんが上目づかいで小さく聞いた。
「人生いろいろって言うじゃない、オレって良くも悪くも大当たりなのかもね……劇的だよ」武の話が止まった。ちょっと間があいて、武は思い切ったように言った。
「尚子の彼氏って、蓮池だったのよ」
「えぇーっ、」皆が一斉に声をあげた。
「そぉ、蓮池と二股だったわけ、尚子としては両方にきっちりとその旨は伝えてあったのだから問題はない。もちろん尚子はオレと蓮池の関係は知らなかったんだが……なんていう運命のいたずら……だから人生いろいろなんだよ。もっと言うとね、それでオレは床屋になったじゃん、尚子を取られた蓮池はどうなったと思う……ヤツは人生を切り替えようと思ったんだ、暴走族なんて子供の遊びじゃなくて、本物、即ちヤクザの組に入っちゃったんだ」と言って武は顔を上げた。
話はそこで終わりになった。重い話だった。ここにいた皆には十年間も話し続けていたような錯覚があった。十年の重さをしょって皆は店を出た。
『完全に昔を思い出した。オレの人生って、人に言いたいような、言いたくないような不思議な人生だな』と、日記を書き終えると武はあおむけになって天井をじっと見た。静かな夜だ。
「こんにちはー、きょうは空いてますか?」平成不動産の唐山さんが突然入ってきた。
「ああ、お久しぶりで、空いてますよ、どうぞ」
「じゃ、お願いします」
唐山さんは会社名の通り、平成元年に創業した不動産屋だ。少し離れた新幹線の(港北駅)近くで開店し、いまではかなり大きくなった。
「あー、気持ちいい、やっぱり床屋はリラックスできるね。そんで終わるとシャキッとする」唐山さんはご機嫌だ。
「どうもどうも、そう言っていただくとこっちもなんかサービスしたくなっちゃいます。缶コーヒーでいいですか?」
「いや、オレ、催促したわけじゃないからね」
「ハハハッ、甘いのでいいですか?」
「ごめん、勝手言って悪いけど、糖尿ヤバイからブラック、ブラックね」
武は唐山さんがコーヒーを飲み終わるのを待って、顔を剃り始めた。
「どうですか、不動産屋の景気は?」武は剃りながら定型の世間話を始めた。
「もうそんなに動きはないね、昔みたいな」
「やっぱり唐山さんが開業したころがピーク?」
「そりゃそうだよ、あんなことはもうないよ」
「不動産屋ってヒマな時、何するんですか?」
「特にないんだよなぁ」
「じゃあ、景気悪いし先行きキビしい?」
「ウーン、一つデカいのがあるんだが、うちが絡めるかっていうと難しいよな」
「ヘー、この近くで?」
「そう、港北新幹線駅のこっち側」
「へえー、でもこっち側に空き地ないじゃないですか。再開発とか言うような古い町でもないし」
「あー、武さん、今の話、ないしょ、内緒にしてくれる?」おっと言ってしまったというような感じで唐山さんは急に口留めをした。
「え、ええ、私、口固いです」といった武であったが、持ち前の好奇心が刺激された。(えー? どこかな?)とちょっと気になる。
『やっぱり平和なのがいい。尚子も落ち着いたし』と書いて、武は思う。このところ平穏な日々が続いている。日記に書くことがないのはいい事なのか、まあ、警察も消防もヒマな方がいい。