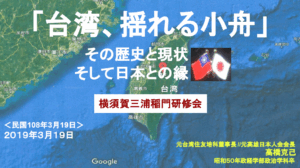▶相国寺展(高22期 加藤 麻貴子)

4月24日東京藝術大学大学美術館で開催されている相国寺展に行ってきました。相国寺は京都五山第二位に列せられる臨済宗の名刹で14世紀末室町幕府三代将軍の足利義光により創建されました。慈照寺(金閣)、鹿苑寺(銀閣)は相国寺の塔頭寺院、優れた禅僧や如拙・周文・雪舟らの画僧を輩出し600年余を地理的にも文化的にも京都の中心にあり続けてきました。墨蹟・絵画・茶道具を中心に多数の文化財が伝来しています。また江戸時代には伊藤若冲という天才絵師を送り出しています。それらの文化財を収蔵展示するための承天閣美術館の開館40周年を記念して上野で相国寺展が開催されています。
10年ほど前の小雪舞う冬のある日、承天閣美術館見学のために相国寺を訪れましたがあいにく休館で残念な思いをしました。広い境内冬木立に囲まれて1605年再建の法堂が巌とした姿で在るのを眺めただけでした。相国寺を知ったのは2011年福島の美術館にプライスコレクションの伊藤若冲展を観に行ったのがきっかけです。そこでの若冲の絵は鳥獣花木図屏風に代表されるような豪華絢爛極彩色。以来若冲のファンになりました。
若冲は京の錦小路高倉の南東の角にあった青物問屋「桝源」の長男として生まれ長じて相国寺の大典顕常と交流、相国寺を始め京都中の寺院の南画(中国画)を模写して腕を磨き40歳を迎えた若冲は家督を弟に譲り、「花鳥三十副」の絹本を相国寺に寄進、その方丈に掲げられ風に揺れる様はさぞかし極楽浄土を思わせると想像してしまいました。今回の相国寺展には若冲の絵も展示されるというので足を運んだ次第です。
1,2階は1408年の足利義満像、雪舟の山水図後水尾天皇像や和歌・筆の墨書などが展示されており、昔の人たちの墨書の堪能なことにため息が出ました。ワープロやPC出現以前の日本では普通の人でも升目もない紙に折り目正しいい文字を書いていました。字を書くのではなく打つようになった今 手書きの文字は残るかとふと思いました。3階は若冲が生きた時代の展示、今回の若冲は力強い玉熨斗図や鹿苑寺大書院の障壁画の葡萄小禽図や双鶏図など墨画ばかりでしたがこれも若冲らしい作品と満足しました。また丸山応挙の七難七福図巻きも魅力的でした。
[ランチ]3時間ほどの観覧のあと、美術館を出ると空腹を感じ、芸大の庭のキッチンカーでロコモコと飲み物を調達広い軒天の下のベンチで食べ始めました。目の前は巨木の新緑芸大生の行きかう風景、大学生気分に浸っていると私と同じくらいの年恰好のご夫婦に相席を求められ、応じるとオニギリのノリの匂いと相国寺展を腐す話にすっかり興ざめてしまいました。普段はノリの匂い大好きなのに・・・。それでも上野公園のケヤキの巨樹の新緑は眩しくプチ森林浴の気分で家路に着きました。
本日の教訓「相席したら黙して食すべし」です。
相国寺展は5月25日まで東京藝術大学大学美術館にて開催しています。7日(水)と月曜日は休館です。
▶相国寺展
相国寺承天閣美術館開館40周年記念 相国寺展―金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史