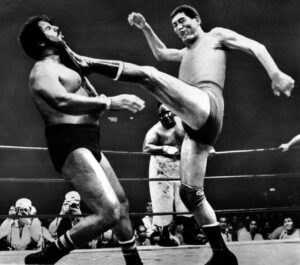▶進次郎大臣に代わって考える「コメの価格」と「農機のリース」(高22期 高橋克己)

レジ袋有料化やベトナムの火力発電といった、環境相としての小泉進次郎氏の対応は全く評価しないが、農水相としての仕事振りは買っている。無茶なところが良い。が、細かいところでは問題もある。例えば「(コメを)じゃぶじゃぶにしてかなきゃいけないんだと、そうじゃなかったら価格は下がらない」とか「農機、リースが当然」発言とか。
「じゃぶじゃぶ」発言には、「安ければいい、の追求では生産者が誰もいなくなる。小泉農水相には、現場を元気づけるメッセージを発信してほしい」とJA秋田中央会会長が苦言を呈した。また「リースが当然」には、農機のシェアリングサービス会社が「コンバインや田植え機は事業化が難しい」とし、SNSでも「使う時期はみんな一緒で、リースできない」との指摘が相次いだ。
が、疑り深い筆者にはこれらの指摘が「本当にそうだろうか」と訝しい。モノが何であれ、価格は需要と供給で決まるから、供給が勝れば価格は下がると相場が決まっている。進次郎氏の課題は「では幾らが適正なのか」まで思考が深まらないところにある。また、「農機のリース」については、そのヒントが台湾にある。以下では、これら二件について書く。
■
コメの価格はどうあるべきか。この問いの解を容易く出し難い理由は、消費者と生産者に思惑・事情の違いがあり、かつ生産者の間でも大規模農家と小規模農家では生産コストに2倍以上の開きがあるからだ。後者では、作付面積が0.5ha未満~1haまでの35.8万戸の生産コストが約27千円~21千円/60kgであるのに対し、1ha~10haの19.5万戸では17千円~14千円、作付面積10ha以上の2.3万戸では12千円~10千円(50ha以上)で、作付面積と生産コストはほぼ比例する(農水省サイト)。
他方、コメの買い取り価格は、一昨年までの10数年間概ね12千円~15千円/60kgで推移して来たが、昨年(24年)は23千円~24千円に急騰した。需要と供給の経済原則に従えば、価格を上げるためには供給を絞る必要がある。つまり、昨年24千円で買い取ると決めた時点で、コメ不足にする必要が生じたのだ。誰がそれをしたかと言えば、「買い取った人たち」以外にはあり得まい。
とはいえ生産コストを考慮すれば、12千円~15千円では35.8万戸の農家は60kg当り1万円近くの持ち出しになる。どう補填して来たのか、門外漢の筆者に真相は判らないが、兼業農家であることや何らかの補助金があったからではなかろうか。逆に、10ha以上を耕作する大規模農家にとって、生産コストに倍する買い取り価格はずいぶんありがたかろう。
そこであるべき売値の話になる。生産者の事情は理解するとしても、安けりゃ安いほど良い、というのが消費者の心理だ。今回の騒動で、古古古米だろうと輸入米だろうと、その味の差は値段の差ほどには大きくない、ということを多くの消費者は知ってしまった。となれば、値段の基準は畢竟「輸入米の値段」ということになる。
輸入米の輸入価格は、米国産の中粒種「カルローズ」でCIF150円/kg程度(CIF:輸送費・保険料込み・日本港渡し)とされる(『読売』記事)。台湾米は、コメの輸出に関わっている知り合いの台湾人によれば、横浜港渡しのCIFで1.2USD/kg程、142円/USDなら170円だ。これに341円/kgの関税が乗って490円~510円、すなわち500円/kg前後が輸入米の仕入れ値である。
他方、国産の銘柄米が24千円/60kgなら400円/kgだから、輸入米から1kg当り100円のハンデをもらうことになる。これらは玄米の価格であって、店頭に並ぶまでには、精米⇒小分け袋詰め⇒冷蔵保管などのコストや段階毎の運賃とマージンが乗る。それらが仮に2000円/5㎏とすれば、玄米で400円x5kg=2000円だった銘柄米が、4000円/5㎏といった価格で店頭の並ぶのである。
が、ここでもし大手の小売り業者が新規参入して流通を簡素化し、輸入・精米・小分け・保管に利益を含めて1000円/5kgで賄うなら、500円x5kg=2500円+1000円=3500円/5kgで店頭に並び、4000円の銘柄米は売れ残る。つまり、3000円台前半から3500円辺りが、国産の銘柄米が目指すべき売値なのである。消費者には申し訳ないが、農家が立ち行かなくなる2000円台の低価格にする必要はない。
■
次は「農機のリース」。私が台湾高雄に在勤していた2013年当時、日本人会の仲間だった某農機メーカーの董事長から「台湾には田植え機や稲刈り機を持つ業者がいて、島中の農家を回って作業を請け負っててるんですよ」との話を聞いた。「それじゃ農機が売れませんね」というと、「そうなんです。補修部品が多いんです」と返って来た。進次郎氏の「農機のリース」でこの話を思い出した。
改めて調べてみるとそれは「代耕」という仕組みだった。進次郎氏が読んだかどうかは判らないが、「『代耕』-台湾稲作における作業受委託-に関する調査」と題する、 JA三井リースと農林中金総合研究所が16年8月に台湾で行った65頁に上る詳細な調査報告書をネットで読むことが出来る。紙幅の関係でその「さわり」を紹介する。
台湾のGDPに占める農業の割合は1.8%に過ぎない。が、総戸数834万戸に対し、農家戸数は78万戸と9.4%を占め、総人口2329万人の12.9%に当たる301万人が農家人口である(15年の農業統計年報)。日本の総世帯数に占める総農家数は 3.8%、総人口に対する農家人口は4.0%である(2015年国勢調査、農林業センサス)。農業を営む台湾人の比率は日本の約3倍という訳である。
台湾のコメ生産量(玄米換算、以下同様)は126万t(15年)で、07年の110万tを底に漸増し概ね120万tから130万t台で推移している。稲作は二期作が普及しており、15年における第一期の生産量は85万t、第二期は41万tである(24年の日本の生産量は679万t)。 稲の種類では蓬莱米(ジャポニカ米)が中心で、15年の蓬莱米の生産量は115 万トンと全体の9割を占めている。
生産量増加の理由として、13年から実施されている「調整耕作制度活化農地計画」がある。この計画は転作と休耕を奨励しているが、休耕の場合は第一期のみが補助されるため、一部農家に第一期は米を作付けようとの意思決定が促された。15 年の単収は5t/haで、第一期が5.8t、第二期が3.9tで毎年第一期の単収が高いが、第二期は台風を避けて作付けを減らしている影響もある。
一方、台湾でも1 人当りのコメ消費量はほぼ一貫して減少してきた。03年に50㎏/人を下回ってから08 年までは48㎏/人前後であったが、11年から45㎏/人台で推移し、15 年は45.7㎏/人であった。日本も同様で、1962年に118kgだったものが、22年には50.9kgまで減少した。筆者の経験でも、日本人と比べて台湾人はご飯以外のもので食事を済せることが多い。
そこで「代耕」のことになる。それは農業経営者に代わって農作業を行うことをいう。中国、韓国や日本でも一部行われている。「部分代耕」と全作業を行う「全部代耕」があり、台湾の主流は前者である。「部分代耕」の作業は、育苗、整地、田植え、肥料、農薬散布、収穫等で、台湾の特徴は各作業に専門業者が存在し、それらの業者が機械を利用して代耕するところにある。これは「機械代耕」と呼ばれている。
少し古い90年のデータが載っていて、「部分代耕」を使って行われる規模別の作業別割合は、「0.5ha未満・・育苗92%、整地91%、田植え92%、収穫96%」、「0.5ha ~1.0ha未満・・育苗91%、整地85%、田植え91%、収穫96%」、「3.0ha 以上・・育苗72%、整地52%、田植63%、収穫87%」である。つまり、「代耕」は規模の大きいほど減少する(機械を所有して自分でやる)ものの、ほぼ大小に関わらず行われていると言って良い。
地域別にみると中部地区(中南部の意か?)が多い。稲作以外も含む農業全体では全台湾では56%余りだが、中部は65.4%で、整地、育苗、田植え、収穫の全ての作業で全台湾に比べ高い。私の知人によれば、台湾は二期作が主流だが、北部は一期作、中南部(台中・嘉儀・台南・高雄)は二期作、屏東以南(恒春)は二期作+その他とのこと。八田興一の烏山頭ダムが潤す嘉南平野は嘉儀と台南に跨っている。
調査報告は、台湾の稲作農家が約21.3万戸である一方、田植え機は19,432台、稲刈り機は9,710台あるから、田植えは代耕業者1社が21戸の農家から、稲刈りは1社が42戸の農家から受託していると、少々大雑把な推定をしている。また、稲刈り機は自脱式コンバイン(穂先だけ刈って脱穀もする)が主で、総台数は05年の19.488台から半減したが、これは機械の主流が2条~6条から6条~8条へと大型化したことによるとある。
最後に、日本で「代耕」が成り立つかどうかを考察してみる。
まず面積と生産量だが、国土面積は台湾が360万haで日本は3,778万haだ。耕地面積は台湾が約80万haで、内訳は水田と畑地が約40万haのほぼ半々。日本の耕地面積は約430万haで、うち232万ha(54%)が水田である。つまり、日本は台湾に比べ、水田面積で5.8倍、生産量で5.4倍あるので、数字の上では「代耕」が成り立ちそうである。
次に田植えと稲刈りの時期だが、これもネットに載っている。
先ず全国の田植えの時期は、地域別におおよそ以下のようだ。
1月下旬・・・沖縄(島嶼部)
3月中旬~下旬・・・沖縄(本島)、九州
4月下旬~5月上旬・・・千葉、三重、滋賀
5月上旬~下旬・・・北海道、茨城、栃木、東北
5月中旬?6月下旬・・・中国・四国・近畿(三重・滋賀を除く)・北信越・東海・関東(千葉・茨城・栃木を除く)
都道府県別の出穂と稲刈りの時期は以下で、概ね9月初めから10月半ばまでに稲刈りが行われるようだ。
地域 出穂 刈取北海道 7.31 9.29
青森 8.5 10.2
岩手 8.6 10.3
宮城 8.6 9.29
秋田 8.3 9.29
山形 8.6 9.3
福島 8.9 10.9
茨城 8.2 9.13
栃木 8.4 9.22
群馬 8.21 10.2
埼玉 8.12 9.25
千葉 7.21 9.1
東京 8.14 10.4
神奈川 8.11 9.29
新潟 8.6 9.19
富山 8.5 9.18
石川 7.3 9.1
福井 8.4 9.11
山梨 8.11 10.2
長野 8.9 9.29
岐阜 8.21 10.1
静岡 8.7 9.21
愛知 8.2 10.5
三重 7.22 9.4
滋賀 8.2 9.16
京都 8.2 9.22
大阪 8.22 10.7
兵庫 8.13 9.29
奈良 8.23 10.11
和歌山 8.6 9.17
鳥取 8.9 9.26
島根 8.8 9.17
岡山 8.21 10.6
広島 8.9 9.26
山口 8.12 9.18
徳島 7.19(早期) 8.22(早期)
7.31(普通) 9.7(普通)
香川 8.2 10.1
愛媛 8.13 9.23
高知 7.2(早期) 8.8(早期)
8.17(普通) 10.2(普通)
福岡 8.23 9.3
佐賀 8.3 10.9
長崎 8.26 10.12
熊本 8.22 10.8
大分 8.24 10.14
宮崎 6.24(早期) 8.8(早期)
8.23(普通) 10.12(普通)
鹿児島 6.26(早期) 8.9(早期)
8.26(普通) 10.17(普通)
沖縄 5.21 6.22(第一期)
沖縄 10.11 11.12(第二期)
台湾は、二期作とはいえ国土は九州並みだから、田植えや稲刈りの時期は南北に長い日本以上に集中するはずだ。21万戸余りの農家があり、経営規模に関わらずその約9割が「代耕」を使っていて、代耕業者1社で20~40戸の農家から請け負っているとすると、少なくとも数千社?は存在するはずの代耕業者の経営が成り立っていることになる。
こうして見てくると、日本でも「代耕」が成り立つようにも思える。進次郎氏は、農家への「農機リース」という視点だけではなく、「代耕」という視点からも、農水省の頭の良い役人に知恵を出させてはどうだろうか。そうこうしているうちに、利に敏い台湾人が経営する「代耕」会社が出現するかも知れませんね。おわり