▶日米関税交渉に一言(高22期 高橋克己)

4月初め世界各国に向けて唐突に発せられたトランプ関税、その交渉が最終盤を迎えています。残るは中国だけかと思われましたが、決着したはずの日本との合意内容ついて俄かに齟齬が生じています。本稿では「合意文書のないこと」と「5500億ドルの投資」について思うところを述べます。
■合意文書
追加関税15%の実施を前にその内容に日米で食い違いが生じました。急遽訪米した赤沢氏が、米閣僚から「手続きは遺憾だった」との認識を示した上で、「今後、適時に大統領令を修正すると説明があった」と述べているので、きっと米政府の事務手続きのミスなのでしょう。が、事務方の首が飛び、実際に修正されるまでは安心はできません。
この関連で「合意文書」がないことについて赤沢氏は、「合意が7月22日で実施が8月1日だから」とし、「文書作成は無理」とドヤ顔で述べていましたので、事実その通りなのかも知れません。
が、私が現役当時に経験した合弁やM&Aの交渉では、その日の交渉の終わりに時間を設け、双方がまとめたメモを突き合せた議事録を必ず共有しました。それを社内に持ち帰って経営幹部で確認し、疑義が生じれば次回の交渉で提起して、そこでの結論をまた議事録に残すのです。国内外どんな企業が相手であろうとそのように事を進めました。
何故なら、こうした交渉では相手の説得にも増して、社内の合意形成が厄介だからです。仮に米側が「省きたい」と言ってきても、こちらから「ダメだ、今日決めたことを確認しよう」というべきでした。そうしておけば、合意文書はこれまでの8回分の議事録を合体するだけなので、言うほどの日数が掛るとは思えません。双方が当たり前のことをしなかったために生じた齟齬ではないでしょうか。
■5500億ドルの投資
日本はどういう成り行きか5500億ドル(約80兆円)もの膨大な投資資金を米国に提供する羽目になりました。トランプ大統領は、投資から得られた「利益の9割は米国、日本は1割」と述べています。しかし、依然としてそのスキームの詳細は明らかではない。そこで筆者ならこうするという提案を以下に述べます。
味噌は、トランプ氏がデスクのフリップの「4000億ドル」を書き換えた「5500億ドル」です。彼がそれを知ってか知らずか、その金額は日本が保有している米国債1.1兆ドルのちょうど半分に当たります。そこで、日本が保有国債を担保に5500億ドルを米国金融機関から借りて投資財団を設け、そこから米国の望む案件に適宜投資する枠組みを提案するのです。
日本が毎年受け取っている米国債の利息は数兆円に上り、所得収支の黒字に貢献しています。保有米国債の半額を金融機関から借りれば、その分の利払いが日本の所得収支を悪化させますが、5500億ドルの投資から得られる利益の1割がその悪化分より多ければ、日本からの持ち出しはないし、所得収支も悪化しません。当然、借入金は借りっ放しとし、もし返済を求められれば米国債の額面現物で行うことにすれば良いのです。
そこで日本が米政府に要求すべきことが他にもあります。一つは、5500億ドルの投資から毎年得られる利益の1割が、金融機関への利払い額を下回らないよう適切に投資させ、それに至らない分は米政府に補填させることです。そのためには米政府が、金融機関に日本への融資利息を低く抑えるよう指導する必要もあるかも知れません。
二つ目は、それらが達成されない場合、「米国債を売ることがある」との一項を、5500億ドルの投資契約に設けることです。彼らは「日本を銀行にした」と言っているのだし、また四半期毎に日米相互関税率の遵守状況をチェックし、違反があれば日本に追加関税を課すと述べているのですから、これくらいのことは要求してもバチは当たらないでしょう。
以上ですが、この種の交渉でのこうしたやり取りは、民間で当たり前に行われていることです。そこで米国の陣容に目を向ければ、不動産王のトランプ大統領は勿論、ベッセント財務長官もラトニック商務長官もウォール街で大儲けした大富豪。こうした実業家相手に、そもそも日本の政治家や役人が太刀打ちできるはずがない。 おわり


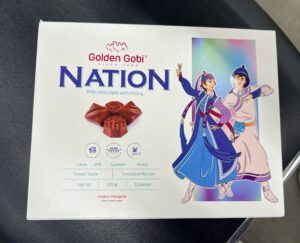
アラスカLNGはやるのだろうか?もう数十年前から、出ては消え出ては消えていた計画で、アメリカの大手は手を引いている。
台湾と韓国は乗り気のようだ。ただ両国とも国営だ。日本は三井物産と三菱商事が主力になるだろうが、政府保証でも無い限りやれないのではないか?何しろ北極から南の太平洋までパイプラインを引く壮大な工事だ。
環境破壊が酷いということで、バイデン政権の時にはこの計画を凍結していた。
固唾をのんで注視している。