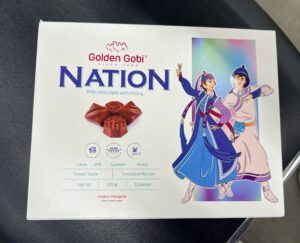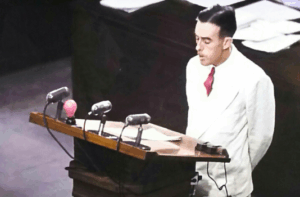▶日本語サロン 1学期終了(高22期 加藤 麻貴子)

7月の第2週まででサロンの1学期は終わりました。ロシアのカーチャは相変わらず無口でボランティアの私たちをどんな風に思っているのかさっぱり分かりませんでしたが6月末に私たちにロシアの絵葉書、チョコレートと小さなマトリョーシカの飾りをプレゼントしてくれました。ロシアに住んでいるマーマチカ(母)が皆のために送って来てくれたとのことでした。感謝の気持ちが伝わってきてとても嬉しく思いました。
ある日「ばかり」と言う言葉を使って文章を作ってもらうと「お母さんは日本にきたばかりなのにもう帰ってしまいました。」ほろりとしてしまいました。尊敬語や謙譲語を難しい、でも試験のために6月は重点的に勉強しました。7月初めに日本語検定試験のN3を受け、まだ結果は出ていませんが手ごたえを聞くと「フツー」と言っていたのできっと合格していると思います。
漫画の「ちびまるこちゃん」を一緒に読み「幽霊」が登場、聞いてみるとロシアには幽霊はいないとのこと、そういう概念がないようです。ついでに埋葬法を聞くと宗教の違いで父は土葬だけど母は火葬とのことで以外でした。
6月から汐入のサロンのお手伝いに行き始めました。夕方ということもあり人数も多く、基地の米人、中国の母子、ネパールの少女など千差万別でした。ネパールの少女は漢字を教えると即座に覚える、それに日本の文字を書く時の「ハラウ」や「トメル」を簡単に理解しました。米人の若者は全てトメて書きハラウを理解してもらうのに少し時間がかかりました。それは英語の書き方に「ハラウ」や「トメル」の書き方がないからでしょう。また、米人は私が「この場合には主語を省いてもいいですよ。」と言ってもけして省きません。英語の構文が反映されてしまうようです。
漢字を教えるとき、筆順に悩むことがありましたが、ある日の新聞に筆順についてのコラムがありました。それによると書家、一般社会、その他の筆順を統一するように昭和33年に文部省が「筆順指導の手引き」が刊行したが、様々な筆順を誤りや否定するものではなくあくまでも手引きであるそうです。合理的で書きやすく感じる順序で良いそうなので私は大変ほっとし、来学期も筆順に悩まず漢字を教えようと思いました。
汐入のサロンにジャマイカの女性が参加しており、授業が終わると「センセ、センセ」と大声で呼ばれ、傍に行ってみると「日曜日に個人レッスンをして欲しい」と請われ躊躇すると、押しが強く承諾するまで粘られました。こういう粘り強さは交渉事には必要 特に日本人が外国に行った時には必要だと思います。