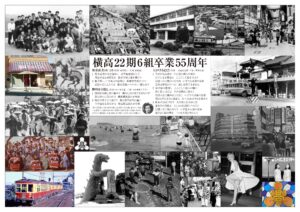▶ 小栗忠順小考(高22期 松原 隆文)

一、再来年のNHKの大河ドラマの主人公は小栗忠順(おぐり ただまさ)だという。
それを聞いて大きな感慨を禁じ得ない。私が若い頃は小栗の評価は否定論が圧倒的であった。五十年も経つとこんなに変わるものなのか?
小栗の評価が否定的であった最大の理由は、例の借款のせいであろう。外国から金を借りてまで幕府の延命を図った男ということだ。石井孝博士なども小栗の能力を高く評価しながらも「買弁的徳川絶対主義」と評している。買弁とは外国資本に追従し、自国の利益を損なう行為であるから、煎じ詰めれば小栗は売国的な人物ということになる。
彼は兵庫商社の設立を企て、兵庫開港後三年もすれば、100万両の関税収入が見込まれていた。だから返済の目途がある借款だったと言える。これを単純に買弁と決めつけるのはあまりにも短絡的ではないか?という考え方が今日の歴史家に徐々に浸透してきたのであろうか。
二、 ここで彼の生涯を語るほどの知識は持ち合わせていないが、思いつくままに少しだけ述べてみたい。
徳川幕府はその最末期になると、親仏幕権派が台頭してきた。そのメンバーは小栗忠順、栗本鯤、向山一履、平山忠敬等である。彼らは等しく優秀で実務能力に長けていた。また徳川絶対主義を貫くという点で守旧派の支持も得やすかった。最末期の幕府をリードしたのは、革新官僚とも言うべきこれら親仏幕権派の面々であった。そしてその中心が実に小栗忠順であった。彼は関東の行財政改革を一身に担っていたが、その政治構想は、徳川勢力によって日本を統一し、全国を郡県制にするというものである。だから必然的に雄藩連合やその発展形とも言うべき公議政体論とは相容れないものであった。また、王政復古により朝廷を担いで幕府を倒し、日本を近代化しようとする薩摩長州を中心とする討幕勢力とは、敵対関係になることが必然であった 。要するに明治維新は、これら二大勢力による日本近代化の主導権争いと言って差し支えない。当時の福沢諭吉も、王政復古などではなく「大君のモナルキ」によって日本を近代化すべきであると述べていた。
彼の政策は後の明治政府が行ったことを先駆けていると言って良いが、幕府が瓦解したため、ほとんどがご破算となった。彼の現代まで続く目に見える遺産は横須賀の軍港である。フランスのヴェルニーが、ツーロン港に地形が似ているということで横須賀を選んだ。また、他の国よりも遙かに低額の建設費を提示したため、フランスに発注したものである。横須賀港は、幕府が崩壊した後も明治政府に引き継がれ、大日本帝国海軍の鎮守府として大いに栄え、戦後も海上自衛隊の基地として今日に至るまで立派に機能している。だから小栗は三浦半島発展の恩人と言える。臨海公園に小栗とヴェルニ-の胸像が建っているのは当然とも言えようか。
最末期の幕府は、急速に近代化政策を進めていたが、特に陸軍の近代化が急務であった。しかし極度の財政難に喘いでいた幕府は、常備軍を整備する財政面でのゆとりがなく、小栗はそれを解決する手段として借款に頼る道を選んだ。これが後世の歴史家に叩かれているのだ。
しかし小栗は借款の返済について、ある程度の自信があったのではなかろうか?その切り札が兵庫開港であった。筆者は兵庫開港問題を何度も取り上げているが、幕府にとってこの兵庫開港こそが、自らの手による日本近代化の切り札であったと言える。
何しろ三年もすれば、100万両の関税収入が見込まれていたのだ。小栗は兵庫開港に備えて、三井、鴻ノ池といった豪商に数十万両の資金を拠出させ、半官半民の兵庫商社を設立し、更にこの基金を担保に100万両規模の兌換紙幣の発行を計画していた。これが順調に進めば、幕府は財政面でも完全に立ち直ってしまう。この小栗の発想は当時誰も思い付かなかったもので、正に革新官僚小栗の面目躍如たるものがある。
また、兵庫開港・大坂開市をすれば、英・仏・米・蘭など当時の欧米大国は、日本の内乱など絶対に望まなくなる。薩摩は、日本近代化の主導権を永久に封じられてしまうのだ。更に、当時の下関は密貿易で大いに栄えていたが、兵庫開港・大坂開市により、諸外国はそんな姑息な密貿易などしなくなる。長州も出る幕がなくなってしまう。だから薩摩は何としても幕府の手による兵庫開港を阻止したかった。この幕末最大の政治課題で且つ幕末政局のターニングポイントになった兵庫開港問題は、徳川慶喜が大奮闘して幕府の管理主導による兵庫開港が決められたが、その顛末は、別稿で、以前に記した。
では話を転じて日本からの輸出品の目玉商品は何であったろうか?これは言わずと知れた生糸である。生糸の生産地が幕府領(いわゆる天領)に集中していたことも小栗にとっては心強いことであった。彼は、当時の武士にしては珍しく物品の流通を正確に把握していた。この生糸を輸出品と切り札として貿易を活発に行おうと計画していたのである。折しもフランスでは生糸の病気が蔓延して壊滅的な打撃を受けており、日本の生糸が喉から手が出るほど欲しかったのである。また蝦夷地の海産物も有力な輸出品目であった。
三、さて肝心の借款はどうなったであろうか。結論から言えば不調に終わったのである。これにはいくつがの原因が考えられる。
パリ万博で幕府は様々な出品をして、日本文化を紹介した。しかし何とその隣の一角では、薩摩が「薩摩琉球国」と名乗って薩摩の物品を紹介したのだ。更に薩摩は「幕府は日本政府ではない」とパリの新聞に書き立て、幕府の正統性を疑わせるキャンペーンを行った。意表を突いたといえばそれまでだが、日本の政争を遠いパリまで持ち込む、正に、成り振り構わぬえげつない行為と言えようか。薩摩は何としても借款を阻止したかったのであろう。
幕府にとって不幸だったのは、フランスがメキシコ干渉に失敗したことである。日本に理解のある外務大臣は更迭され、対外政策慎重派の大臣が就任した。第二帝政は明らかに下り坂となり、対外政策は縮小され、日本への肩入れに及び腰となった。
この借款の構造は複雑で未だ解明されていない。分かっているのはフランスが直接幕府に資金を供与するのではなく、フランス輸出入会社を設立し、そこから資金を提供する予定であったらしい。しかし、当時ヨーロッパ全体が不況に陥り、資金が集まらず会社の設立が思うように進まなかった。幕府は状況打開のため栗本?を特使として送り込み、蝦夷地の海産物の開発権を担保に借款を進めようとしたが結局頓挫したのである。
ところでこの借款計画は秘密契約であった。幕府は瓦解時に全ての文書を処分したので、日本側には何も残っていない。フランスはソシエテ・ジェネラール銀行が主力であったが、158年経った今でも議事録を公開していないので、この条約は謎のままだ。
この借款が最終的に破断したのは慶応3年12月である。しかし慶喜は逸早くこの状況を知っていた。それは駐英国公使格の向山が、慶応3年7月15日にロンドンから小栗に電報を打ったからである。「クーレーより金あらす。直ちにオリインタルバンクから為替組むべし!」とである。600万ドルの借款契約をしたフランス側の当事者は、このクーレーであった。徳川昭武のフランス駐留費についても「何の心配もない」と豪語していた彼が手のひら返しをして、民部卿(昭武)の滞在費が底を尽きつつあった。オリエンタルバンクから滞在費用を振り込んで欲しいという電報であった。筆者は、小栗そして慶喜が、何時借款の不調を知ったのか、なかなか分からなかったが、数年前「小栗日記を読む」という書籍を購入し、そこに上記の電報のことが記されていた。船便では数十日掛かるであろうが、電報だと筆者の想像では、ロンドンからカサブランカ、カイロ、テヘラン、カルカッタ、ボンベイ、サイゴン、上海経由で江戸に着くとして数日であろうか? この当時電報があったとは、驚きである。
討幕勢力との軍事衝突の危機が高まる中で、借款が不調に終わったことは、徳川勢力による日本統一を目指した幕府には大きな痛手であった。慶喜が内乱防止のため、大政奉還に打って出た大きな要因になったと考える。
四、さいごに徳川慶喜と小栗の関係について述べてみたい。
小栗は、先述したように、徳川勢力単独で日本を近代化しようとしていた。この点は慶喜も同様であった。しかし関東にいて行財政改革をまっしぐらに進めようとする小栗にとって慶喜は分かりづらい存在であったのではないか?慶喜は政争渦巻く京都にずっと滞在し、江戸に帰らなかった。というより江戸に帰れる状況ではなかったのだ。慶喜は権謀術数を駆使し、反対派からは、「百端の人」とか「譎詐無限」と恐れられた。昨日と今日と言うことがまるで違った。これは慶喜が望んだことではなく止むを得ずやったことではある。しかし小栗にとっては理解不能だったのではなかろうか?現代のように電話も何にもない時代で、江戸と京都は大いに離れている。通信手段が手紙しかなく、お互いの意思の疎通が困難であった。
慶喜が徳川本家のみ相続して将軍就任を渋っていた慶応2年9月上旬、小栗は上京して慶喜に拝謁している。ここで話し合われたのは、江戸の行財政改革の進捗状況の報告、借款契約の確認等であったことが推測される。小栗は、慶喜が自らの手で日本を近代化しようとする強い意思を持っていることを確認し、慶喜は小栗を通じて江戸の親仏幕権派の革新官僚達をその支配下に納めたものと推測される。慶喜が将軍に就任したのはその後の12月5日であった。
五、慶喜と小栗の最後の会談 シミュレーション
しかし小栗の得意の時代は長く続かなかった。徳川勢力は、薩摩の挑発に乗せられて、鳥羽伏見で惨敗し、慶喜があっさりと江戸に当帰したからである。慶喜は悩んでいた筈である。その証拠にロッシュ(フランス公使)とも会見している。ただロッシュの援助を丁寧に断っている。外国勢力の干渉を恐れたのであろう。
慶応4年1月、小栗は押して慶喜に拝謁を求めた。以下、筆者の推測である。
小栗: 上様、箱根で敵を迎え撃ち、幕府伝習隊を出動させ、海軍を駿河方面に展開させれば
敵は袋のネズミ、一網打尽であります。ご決断を!
慶喜: ・・・・・・
小栗: 玉を担ぐ偽官軍に、などて我らが服従せねばならないのでしょう!
慶喜: ・・・・・・
小栗: 上様年来の主張であらせられた御自らの手による日本近代化の夢は如何せられました !
慶喜: 忠順、錦旗は上がったのじゃ!(退席を始める。)
小栗: (なおも慶喜の袖をつかんで放さない。)
慶喜: 罷免じゃ!
この後、慶喜は上野寛永寺の大慈院に籠もって、謹慎生活を始めた。
罷免された小栗は知行地の上州権田村に向かった。その後の小栗の悲惨な最期については、これを語るのを控えたい。