▶第56回端唄協会合同演奏会に出演しました(高22期 新藤久典)

去る8月14日、本ホームページに掲載させていただきました「江戸端唄の紹介」でもお知らせしまたように、10月10日(金)に開催された、端唄協会主催「第56回端唄協会合同演奏会」に出演し、唄2曲と三味線伴奏2曲を披露させていただきました。当日は、同級生の女性が5人も駆け付けてくれて、楽屋見舞いまで頂戴し、大変感激しました。演奏後お会いして感想を聞きましたところ、皆さん初めての経験だったようで、とても喜んでいただき、私も嬉しく思いました。
現在、東京には13人のお師匠さんたちが「端唄協会」を結成し、毎年10月初旬に、中央区日本橋茅場町にあります東京証券会館ホールで、合同の演奏会を開催しており、今年で56回を数えました。私は平成30年から、途中コロナ禍での中止をはさんで、連続で出演させていただいています。
今回は、『嘘と誠』と『づぼらん』の2曲を唄いました。以下に、歌詞と解説を紹介します。
『嘘と誠』
嘘と誠の 二瀬川 だまされぬ気で だまされて 末は野となれ 山となれ
わしが思いは 君ゆえならで 三俣川の 舟の上 心の丈を 御察し
【解説】
この端唄は、仙台藩の三代目当主伊達綱宗が、吉原の花魁に血道を上げ、身請けしよう強く迫りましたが拒否され、それを恨みに思い、船の中で、吊るし切りにして惨殺した事件を題材にしています。この端唄で描かれている場面は、惨殺する直前に、綱宗が未練たらしく花魁に己の思いの丈を切々と口説いているところです。
この端唄は、歌舞伎などで有名な『伊達騒動』に描かれている内容に題をとって作られています。しかし、これは史実ではなかったようです。確かに、綱宗は酒色に溺れ、21歳で幕府から隠居を申し渡されほどの愚公ではありましたが、ここまでの乱暴狼藉はなかったようです。
ちなみに、惨殺されたと描かれている相対(あいたい)は、2代目の高尾太夫で、別名「仙台高尾」です。この源氏名は吉原・三浦屋に伝わる、吉原の太夫の筆頭とも言えるもので、江戸時代に11代を数えました(吉原の三名妓は、高尾太夫の他に「吉野太夫」・「夕霧太夫」があります)。
『づぼらん』
かかる所へ 葛西領なる篠崎村の 弥陀堂の 坊様が 雨降り 揚句に 修業と 出かけて
右に数珠持ち 左の肩には 大きな木魚 横っちょに抱えて ナムカラタンノウトラヤアヤ
おらがかかは づぼらんだよ 隣のかみさんさん これもんじゃ
何のかんのと 修業は よけれど
遙か向こうから 十六、七なる 姐さんなんぞを ちょいと また 見初めて
ヨイヨイヨイ ヨイトコナ よっぽど女にゃあ 野良和尚 面白や
【解説】
この端唄は、実際に存在した人物を描いたものではありません。「生臭坊主」という僧侶を揶揄する言葉があるように、いつの世も、庶民の目からは奇異でおかしげではあるが、どこか愛嬌があり、憎めない僧侶は存在したようで、そうした架空の僧侶の姿を描いたものです。
場面の設定は、現在の東京都葛飾区篠崎(江戸時代は葛飾は下総郡にあり、江戸ではなかった)にあったお寺の、鼻の下が長い坊さんを主人公とした唄で、18世紀後期に作られ、昭和になって寄席や酒席で演じられるようになりました。現在では、三遊亭好楽師匠が出囃子として使っています。
づぼらん=近世の上方の方言で「づんべらぼん」「づんぼらぼん」など、凸凹や突き出た部分がなく、「つるつるなさま」「のっぺりとしたさま」を表した言葉が語源のようです。
ナムカラタンノウトラヤアヤ=南無喝??那?羅夜耶。「大悲心陀羅尼(だらに)経」、「千手陀羅尼経」などの冒頭にあり、サンスクリット文は「ナモー・ラトナ・トラヤーヤnamo ratna trayaya」で、その意味は「三宝(仏・法・僧)に帰依し奉る」です。この陀羅尼を唱えることによって、あらゆる苦しみが軽減され、悪業が浄化されるとされています。(出典:小学館「日本大百科全書」)
このように、端唄は虚実ない交ぜにして、人間の心の裏表を覗いてみたり、人間の姿を面白おかしく描くことで、日々の生活の憂さを晴らしていたようです。
【ご紹介】
江戸端唄の大きな演奏会は年2回開催されています。来年度の開催日は以下のとおりです。興味のある方はご連絡ください。入場券とプログラムをお送りします。
○報知新聞主催「報知端唄鑑賞会」
令和8年4月26日(日) 会場:浅草公会堂(最寄駅:「浅草」駅)
○端唄協会主催「端唄協会合同演奏会」
令和8年10月9日(金) 会場:東京証券会館ホール(最寄駅:「茅場町」駅)
※連絡先 新藤久典
自宅住所 (〒207-0016)東京都東大和市仲原3-13-4
携帯電話 090-4382-5896
E-mail hshindoh@aol.com(半角の@に置き換えてください)

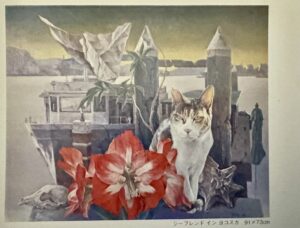

新藤さん、ご招待頂きありがとうございました。同級生5人で初めての端唄鑑賞で「和」の世界に浸りました。「ずんべらぼん」「づんぼらぼん」の音が面白く陀羅尼経の冒頭にあるとは可笑しさを感じました。新藤さんがこのような趣味を奥様とご一緒に楽しまれていることも少し意外でした。また皆でお伺いしたいと思います。