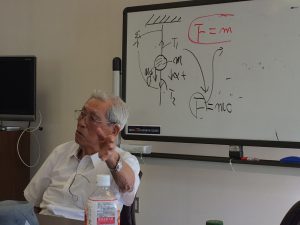▶I君のこと(小川省二先生)
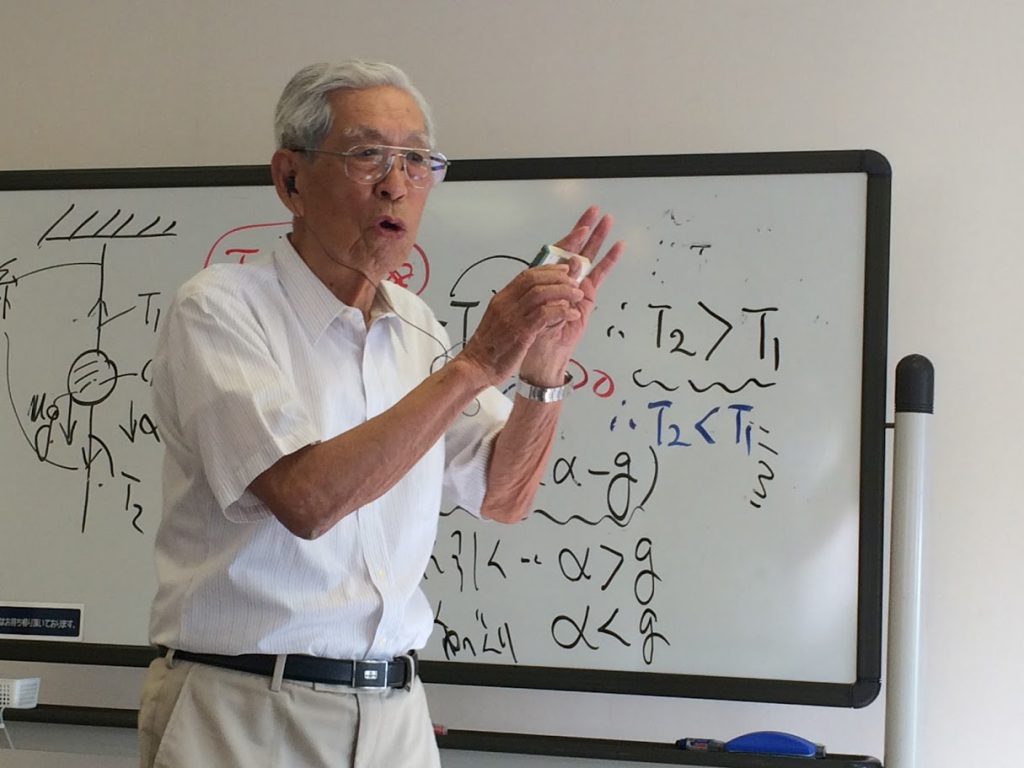
六十半ばを過ぎた私の弟にI君という大学時代からの親友がいる。彼らの家族ぐるみの深い付き合いは四十年以上も続いている。
そのI君は学生の頃、月に一度は東京の下宿から横須賀の私の実家にやってきた。やって来ると一週間から十日は泊まっていく。彼の顔の造作はギョロ目と出っ歯気味の大きな口がその大部分を占めている。それに二十代とは思えぬ柔らかい物腰と、喉の奥から出す男にしては細い声で話をする。一言で言えば、風采の上がらぬ田舎青年ということになる。ただ、彼は大変な勉強家で一日の大半は読書で過ごし、顔を合わせるのは食事の時か、何か判らぬことがあると私のところに本を持ってやってくる位で、あとは部屋に入ったきりである。そうした彼を私の両親は何故か気に入って、昭和三十年の初めの頃だからまだ食糧難の時代であったのに、I君が来ると「よく来たね」とそわそわと迎え入れていた。
ある時、大学から帰った弟が服も着替えずに自分の定期券を封筒に入れて宛名書きをしているのを見た。すると、その翌々日、例のI君が「御免下さい、又来ました」とやって来る。つまり弟とI君は共謀して切手代だけで不正乗車をしているのである。後で聞いたのだが、帰るときは一つの定期券で実に巧妙な手口で四ツ谷駅までキセル乗車をしていたらしい。「電車賃がないなら俺が出してやるからそんな事はよせ」と私は注意したのだが、二人はニヤニヤ笑って取り合わなかった。
その頃の私の家には、常に何人かの人間が泊まりも含めて頻繁に出入りしていた。弟の友人達、私の教え子、同僚、先輩達である。この人達の面倒をみたり、食事の世話をしていたのが私の二人の妹で、特に下の妹(千鶴子というのだが)は『チーちゃん』とか『チコさん』とか呼ばれて、皆にとても可愛がられていた。ある時、弟から、どうやら千鶴子にI君が惚れているらしいと聞かされた。I君が大学を出てから何をやっているのかは定かではなかったが、それでもなにがしかの収入はあるらしく、何かと理由をつけて妹を東京まで芝居見物などに連れ出しているらしいという。その頃、私はもう独立して別の所に住んでいたが、そこにもI君はよくやって来た。来ると三歳の私の娘に必ず、当時流行のグッズものの人形とか鉛筆、筆入れなどを持ってくる。
ある時などは、「今度出す演劇のシナリオです」と渡されたものを見ると、ヒロインに娘の名前を使っている。つまり将を射んとして馬の子供にゴマを擂っているのである。
それから暫くして、又やって来たI君が、「NHKの依頼で書いた脚本なんですが、まだ誰にも見せていません、お兄さん。」「おいおい俺は君のお兄さんではないよ。」「でもお兄さん、是非目を通して下さい。お兄さんが良いと言ったら、持っていこうと思っています。お願いします。」で、そうかと預かった。何日かして、読んだよと知らせると、早速、I君がやって来た。「NHKはお堅い番組が殆どだから、今の時代こういうおふざけとペーソスのミックスはいいかもしれないね。まあ、良くかけていると思うよ。」と言うと、「そうですか」とI君は喜んで帰っていった。私はその後ろ姿を見ながら、ああ俺にも間もなく口の大きな甥や姪ができるのかなと思った。
丁度その頃、私宛の1通の手紙を受け取った。教え子のOからのものであった。手紙は書き出しから妹への恋情が綿々と綴ってあり、手紙の最後に「もし一緒になれないなら僕は死にます」とある。Oは私の愛弟子である。高校時代いつも私の後ろにくっついてゾロゾロ歩いている七、八人の生徒がいた。皆から金魚のウンチとよばれたグループの中の一人である。Oは、口数少なく控えめで、気がつくと友達の後で笑みをたたえている穏やかな人柄の人間であった。勿論、私の家には何人かの友達と来ていたが、妹に対する気持ちなどオクビにも見えなかったことであり、この手紙に私は少なからずうろたえてしまった。特に最後にあるやや脅迫的な『僕は死にます』という言葉からは、もしかしたら、Oならやりかねないという不安を私は感じた。というのは、彼の大学受験の時、Oは東大理1に現役で合格したのだが、同じ理1を受けていた例のグループの人が失敗してしまった。するとOは「僕も浪人します。受け直して彼と来年一緒に行きます。と、私とその友人の二人で説得するのに手こずったことがあった。その時、普段のOに全く見られない、激しく燃えるものを実は内に持っているのだなと感じたのであった。(Oは大学を卒業後、国家公務員上級試験も最上位で通り、希望した職種で社会人として自立した)
早速、妹を呼びOからの手紙を見せて、「どうする」と言うと「IさんもOさんも私にはもったいない方達です。私には決められない。お兄さんの言う通りにします。」I君が足繁く私の所に来たり、Oが妹に直接ではなく私に手紙をしてきたのも、二人とも妹のそうした性格を見抜いてのことだと判った。「どちらも良くて決められない、そうか、それなら私の考えを結論から言うよ。お前はOのところにいったらいいと思う。I君は優しいし、正義感も強い、気持ちの真っ直ぐな男だ。お前を生涯大事にしてくれると思う。それに彼の文学に対する情熱と溢れる才能は只者ではない。必ず将来日本を代表する作家になるのは間違いないと私は思う。が、そうした彼を仕事柄四六時中支えることがお前さんに出来るかというと、一寸荷が重すぎる気がする。その点、Oなら何の取り柄もないお前さんでも何とか務まるだろうし、平穏の中で幸せにしてくれること請け合いだな。どうする、それでいいか。」こうしてI君は私の妹に振られた形となったのである。
Oは現在、地質学特にウランの鉱脈に関する研究では日本の第一人者であり、その学識は海外での評価も極めて高い。夫妻の家庭生活は、三人の美しい娘と三人の孫に囲まれて、平凡ではあるが幸せな毎日を送っている。
さて、I君であるが、大学在学中から手掛けいた子供向けのラジオドラマ、ミュージカルの制作から始まった作家活動は十年を経て、演劇脚本作家としての地位を次第に築いていった。その間、ユニークな長、短編小説も数多く発表しており、昭和十七年岸田戯曲賞、芸術選奨新人賞を受け、同じ年、別冊文藝春秋に掲載した小説『手鎖心中』で第六十七回直木賞を受賞することが出来た。時に、I君三十八歳であった。
六十歳半ばの現在も、本職の文筆活動の傍ら、社会問題、政治問題、教育問題に関心が深く、何かあるとテレビに登場する。東北訛りが抜けず訥々とした語り口で喋る。しかし言い分は諂うことなく率直な意見を述べてゆく。
贔屓目だろうが、その飾らぬ風貌が何とも言えず私は好きだ。今住んでいる地域の環境問題にも熱心らしく駅頭でビラを配ったりしている姿を新聞で見かけたことがある。美空ひばりや渥美清が亡くなれば、何か知っているはずだと思うのか、マスコミは彼を表に引っ張り出す。その度に新聞やテレビの画面でI君の例の顔と声に出会うことになる。本職を 忘れるなと言いたい位行動は多岐に渡っている。私は新聞、雑誌に載る彼の論旨、テレビでの発言の内容にいつも感じるのは、昔と変わらぬ青臭い若さである。『いつまでそんなことを言っているんだ』という思いと、『いつまでも青臭い少年の心を無くして欲しくない』という思いが交錯して、複雑な気持ちになることがよくある。
I君とは、作家井上ひさし君のことであり、昔、彼が私のところに「まだ誰にも見せていないんですが」と持って来たNHKTVへの脚本の題名は、後に大ヒットした『ひょっこりひょうたん島』である。TV放送が始まったのは、四年後の昭和三十九年であった。 つい最近、井上君からもらった手紙に、冥土の両親が聞いたらさぞや喜ぶだろうと思うことが書いてあった。「 ・・・三度三度の食事もご馳走づくめで・・・ご両親はいつもにこにこしておいででした。あんな楽しい毎日ってありませんでした。もし過去に戻れるものなら、私は第一番に『あの頃の小川家』を選びます。(小川省二)
・神奈川県立高等学校退職校長会 友朋会第二十六号(平成十四年九月一日)